
動物介在教育・療法学会
Asian Society for Animal-assisted Education and Therapy

主に家庭動物を対象に、人・動物・環境に安全で持続可能な、適切な動物飼養の普及啓発に取り組んできました。現在、日本における人々と動物のかかわりの原点を追っています。その歴史的背景を理解することを出発点に、欧米由来のAAIを日本で普及するための仕組みをASAET会員のみなさんと考えていければうれしいです。
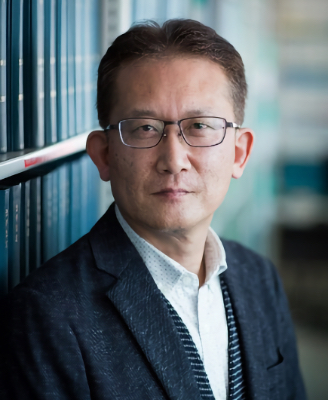
動物介在教育・療法学会(ASAET)の副理事長を拝命いたしました安藤孝敏です。私は、この学会の前身である「日本動物介在教育・療法学会」の設立時から参加しており、理事の一人として継続して学会の運営にかかわってきました。今後は、副理事長として、学会の発展と動物介在教育・療法の普及に尽力してまいる所存です。特に、動物介在介入の科学的知識の蓄積を目指す研究者と、社会実装における現実的課題に取り組む実践者が緊密な連携のもとに自由に意見交換できる場が必要であると考えています。
皆様と共に、動物介在教育・療法の未来を築いていけることを楽しみにしております。今後とも、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
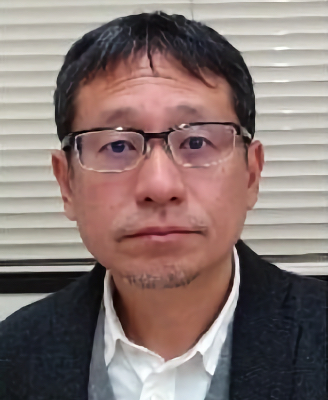
専門は心理学(実験心理学、生理心理学)であり、動物介在介入の効果について心理学的手法を用いた検討をおこなっています。ASAETの強みは、動物介在介入の研究者だけでなく実践家が多く参加していることです。本学会が「研究」と「実践」をつなぐ架け橋として機能することで、人と動物の相互作用がもたらす可能性を社会に伝えていきたいと考えています。
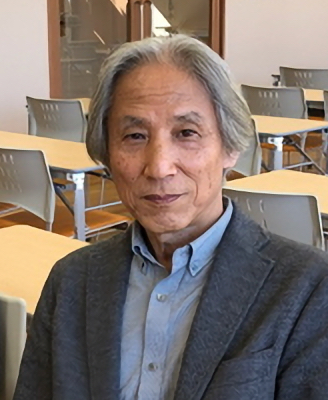
かわさき犬猫愛護ボランティア(平成17年~)の活動と並行して、動物との共生を考える連絡会幹事 運営委員(平成22~27年)、川崎市動物愛護センター懇談会委員(平成23~25年)を経て川崎市いのちの教育に係る意見交換会委員(平成27年~)を務めています。

「モンゴル草原生態系の持続性と遊牧の関係」を中心とした研究活動を経て、社会福祉法人南高愛隣会のホースセラピー研究センター所長に就任。
現在、馬の自然性に配慮した昼夜放牧が、馬たちの福祉向上と障がい者の馬活動の多様化に及ぼす影響の実証調査及び情報提供に取り組んでいます。
また、動植物間の相互作用が景観と環境保全へのフィードバック効果を環境教育とエコツーリズムに活かす方法を模索しています。

小児の作業療法士として、知的障害児の機能改善に乗馬が使えるのではないかと2000年ごろに研究を始めたのが、この領域との出会いでした。また同じ時期に、またドルフィン・キャンプという、自閉症児に対するイルカとのふれ合い活動などにも参加しました。人には出来ないけれど、動物には出来ることがあると信じて、この活動を見守っております。コロナ渦で様々な社会的な変化が生じており、今後リアルな体験が求められると考えると、継続していくことが力になると思います。作業療法士の養成教育の中に少しでも、動物介在のことを含められると、さらにリハビリテーションが充実すると思いますので、今後もよろしくお願いいたします。

最近は、日本の人と動物の関係の歴史について国際学会等での発信を行なっています。また、日本の研究者がもっと積極的に研究成果を国際学会で発信できるような仕組作りを考えています。

学校における動物と児童の関わりの場について考えたことが、ASAETとのご縁の始まりでした。こんにち、動物介在教育・療法は教育や医療の場をはじめ様々な場で実施されていますが、それぞれの状況において適切な環境が整えられることによって、より円滑な展開が実現できる場合もあるのではないかと考えます。また、それら環境は物理的のみならず心理的側面も含めて考慮することが重要です。私の専門である建築設計分野の知見を活かし、また設計者としての経験に基づく具体的提案の視点をもって臨むことにより、お役に立てればと思います。

厚生労働省および日本医療研究開発機構における疲労関連研究班の代表研究者として、疲労の分子神経メカニズムの解明や診断、治療法の開発を担当してきました。以前、不登校、引きこもり児童の研究班におきまして、馬介在療法の効果を科学的に検証したことがきっかけで、動物介在教育・療法学会(ASAET)におきまして、主に馬介在療法を担当致しております。自分自身も乗馬の魅力を実感しておりますので、馬介在療法の効果を客観的に評価したい場合などは遠慮なくご相談ください。

助産師、看護師として、病院で産婦人科、小児科、内科、外科、救急等の勤務を経て大学教員となる。犬を介在させ小中学校や高校で性教育などを行っています。

2024年度から引き続き理事を務めさせていただきます、日本獣医生命科学大学の生野です。
動物介在教育・療法は、人の専門家だけではなく動物の専門家も必要です。愛玩動物看護師は、動物を“看る”力を持っていることから、介在諸活動に愛玩動物看護師が参加することは、よりよい活動の一助となると考えています。動物介在諸活動が多くの方に認知されるよう、そして、ASAETのさらなる発展のために尽力させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
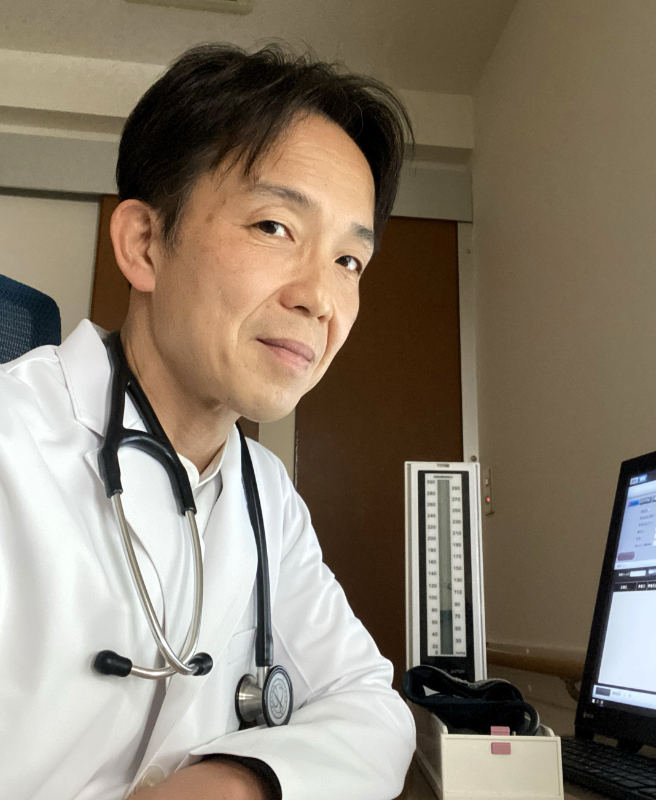
1995年から2010年まで大学病院で診療・研究・教育に従事した後リハビリ病院、訪問診療クリニックなどに勤務。現在は神奈川県横浜市の医院で診療を行うとともに動物介在療法(AAT)の研究を行っています。人間側の医療者は人間への治療効果を優先したAATを行いがちですが、動物愛護・福祉を第一に考えるAATの発展を目指しています。関係団体と連携しAATが行える医療・介護施設を増やし多くの人にAATを知ってもらう、そして研究者とともに質の高い研究を行い国内さらには世界に発信できるよう尽力いたします。

2001年より与那国島でヨナグニウマの保存活用活動に携わり、その後、ヨナグニウマ3頭を連れて沖縄本島への普及活動を開始。2009年にヨナグニウマの牧場「うみかぜホースファーム」(南城市)を設立。2017年に一般社団法人ヨナグニウマ保護活用協会を設立し、代表理事に就任。
現在は代表理事を務めながら南城市のホテルにも所属し、動物介在教育・療法や観光乗馬を通じた地域活性化に取り組んでいます。趣味は街歩きと食べ歩き。地域文化を楽しみながら、ヨナグニウマの魅力を伝える方法を模索しています。

大学では馬術部に所属し馬中心の生活を送り、寄生虫学教室で牛の寄生虫の研究をしていました。小動物の動物病院を開業し30年以上。最近は病院をスタッフに任せ、もっと獣医師として社会に貢献できることがあるのではないかと模索中。現在は、東京簡易裁判所の調停員としてペットに関する調停や杉並区獣医師会副会長をやらせて頂いて、学校動物、ペット防災、飼い主のいない猫などの事業も。微力ではありますが、ASAETの発展の為に尽力してまいりますので、ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。

大学で「心理学」、「教育相談」、「獣医倫理学」、「人と動物の関係学」等を担当し、「人とコンパニオンアニマルの関係;愛着とペットロス」、「動物介在教育・療法」等を研究しています。また、「ペットロスグリーフカウンセリング」を行っています。これらの経歴を活かし、理事として当学会に尽力させて頂きます。
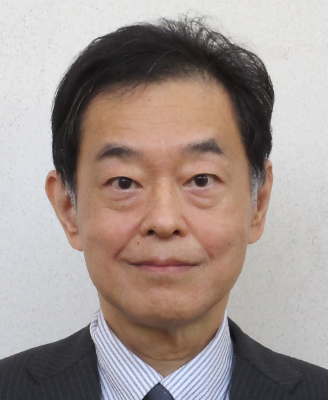
公衆衛生獣医師として動物愛護管理業務などに従事しています。仕事柄動物介在活動に関心を持ち、ASAETに入会し勉強させていただきました。その後動物愛護センターで動物介在教育に携わることになりました。現在は保健所で野犬や野良猫の問題、そして多頭飼育や動物虐待といった課題に取り組んでいます。人と動物が共に幸せに暮らせる社会を目指し、行政マンそして獣医師としての視点から、人間と動物との関係について日々考えています。よろしくお願いします。

専門は社会心理学です。自分の意識や感情をどのように捉え、調整、評価するかといった自己過程が、個人の意思決定や行動、対人関係、精神的健康に及ぼす影響を研究しています。具体的には、自己過程と余暇活動(特に旅行行動)との関連、マインドフルネス、動物介在介入が自己認識や心理的適応に与える影響など、社会的文脈の中での自己のあり方やメカニズムを探究しています。動物介在介入の研究は、犬や馬を対象に行っています.これらの研究と教育を通じて、人々のウェルビーイング向上に貢献することを目指しています。
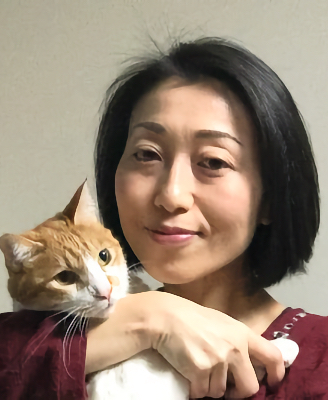
元々は「高等教育」の分野で大学生の発達や大学教育改革について研究していましたが、《一頭の野良猫との悲しい出来事》をきっかけに「人と動物の関係学」の分野でも研究を始めました。研究を始めた当初は「大学生のメンタルヘルスケアに有効な動物介在プログラムの開発」というテーマで、猫を介在動物とする可能性について研究していました。その後、「高齢者と伴侶動物の幸せな共生」をテーマに研究を行い、現在は馬介在活動と学生の発達を絡めて「人と馬の豊かな共生」を目指すプログラム開発にも取り組んでいます。同じ命あるもの同士の交流を通して、人も動物も幸せになっていくことを追究する研究を、これからも続けていく所存です。
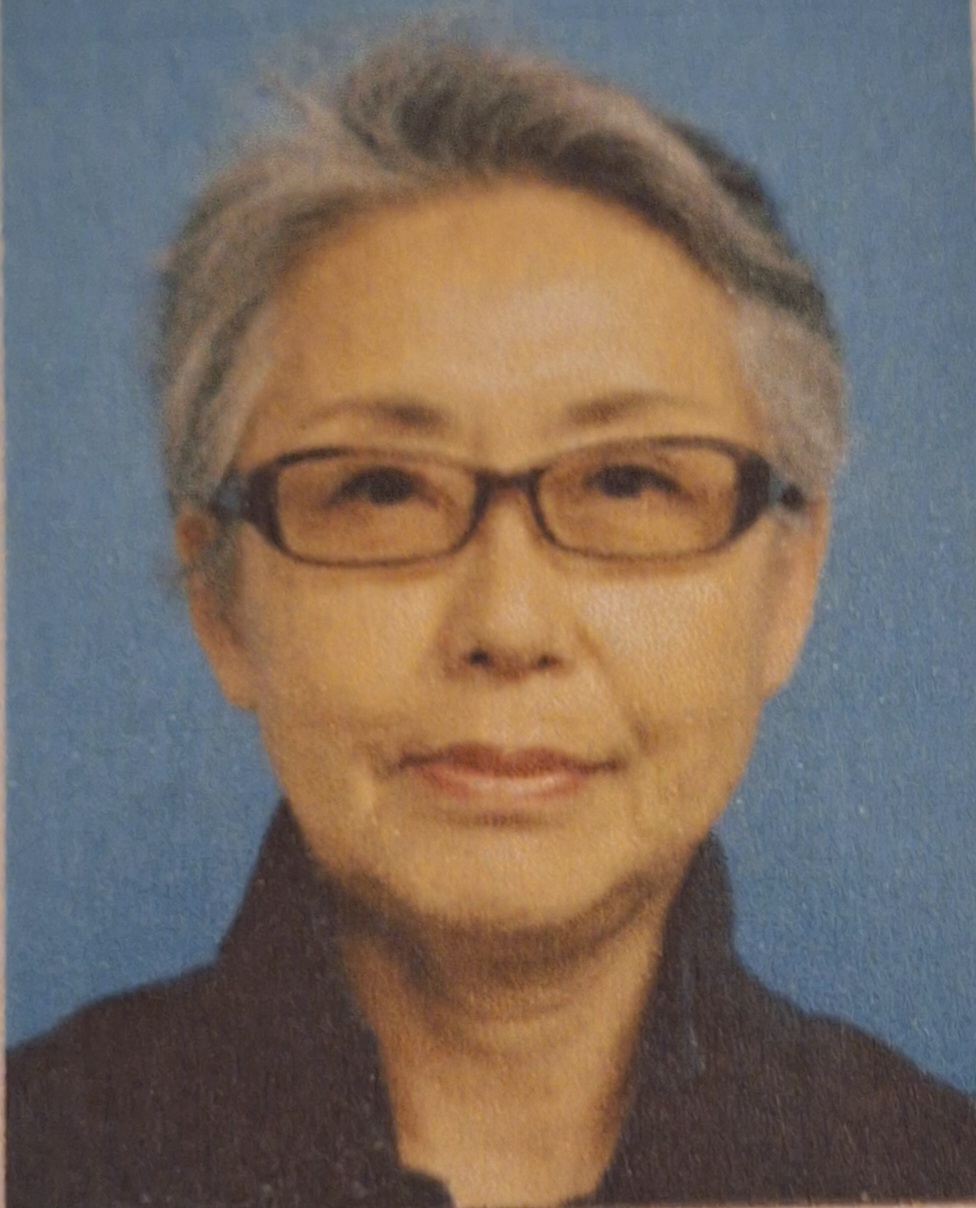
川崎市の条例に基づいた「かわさき犬猫愛護ボランティア」活動で、子どもたちを対象に行政担者と共に動物愛護の普及啓発を行ってきました。2015年ごろより高齢者とペットの問題が顕在化しはじめたことを受けて研究会を立ち上げ、各専門分野の方々の協力を得ながら運営し現在に至っています。社会構造の変化に伴い高齢者とペットの問題も複雑化しています。子どもの頃から生き物との関わり方を伝え、来たる超高齢社会で人と動物が互いに負担なく共生していけるよう、啓発活動が出来ればと考えています。